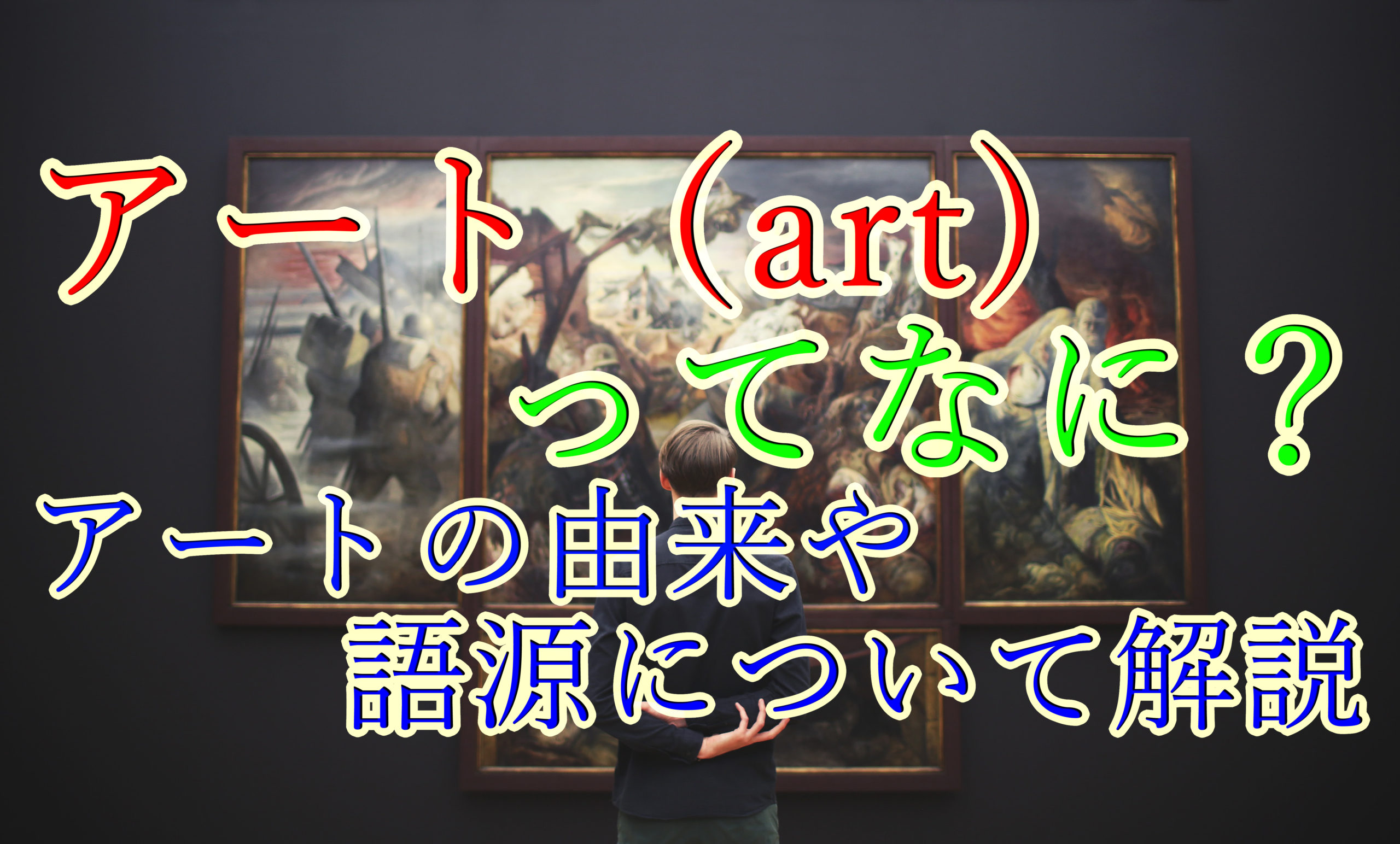「アート(art)の由来や
語源について教えてほしい」
アートは当たり前に使われる言葉として日本で定着しています。
そんなアートはどのようにして日本の言葉として定着したのか
語源や由来について深掘りをしていく中で
詳しく解説していきたいと思います。
アート(art)ってなに?【アートの由来や語源について解説】
![アート(art)ってなに?【アートの由来や語源について解説】]()
『アートは間接的に社会に影響を与えるもの』
アート=芸術という認識の人がほとんどだと思いますが
アートという言葉は幅広い意味を持っています。
人が生きていく上で必要な技術や知識など
自然とは真逆の人工的に作られたものによって影響を与えるものとされていて
それは美術的な分野以外の領域にまで広がります。
そんな抽象的でありながら人間にとって重要な意味を持つ
アートについて深掘りしていきたいと思います。
◆アートの語源
『アートの語源はラテン語のars』
arsという言葉は
「技術」「才能」「資格」といったように
一つの言葉で様々な捉えられ方ををする意味を持っています。
技術によって人や社会に役立つものを生み出したり
才能によって普通は気付かない意味や意図を生み出したり
資格によって価値が上がる環境を生み出したり
arsという言葉は、今のアーと(art)という言葉に
直接的ではなくても間接的に繋がる解釈ができ
それが形や捉え方を変えて伝わってきました。
◆アートの由来
『科学の進歩と共にアートという言葉の捉え方が変わりました』
arsは英語に組み込まれていく中でartになり
それでも意味合いは「技術」で変わりませんでした。
それは全ての学問に共通する言葉として使われてきましたが
産業革命以降、科学技術が発達した事をきっかけに
technologyという言葉が浸透して
「実用性のあるものをテクノロジー」
「実用性のない美的なものをアート」
と分類するようになったとされています。
日本におけるアートの役割
![日本におけるアートの役割]()
『アートは曖昧でよくわからないもの』
今の日本ではアートという言葉が乱用されていて
「○○アート」だったり「アートっぽい」みたいな
抽象的で曖昧でよくわからないけど
アートをつければおしゃれといったイメージが定着していると思います。
欧米のようにアートの歴史や文化があり
子供の頃から教育によって
しっかりとした概念を持っている環境とは違い
日本ではアートの歴史はあっても文化として
日常生活にまで根付いているかというとそうではありません。
そんな曖昧な状態で使っている事もあり
実用性のない曖昧なものという枠から一歩外に踏み出すことができず
アートの価値が上がりにくい環境になってしまっていると言えます。
欧米のように生活必需品として
アート作品を日常に取り入れる為には
意味やメリットを明確にする概念から学ぶ必要があります。
今日本に必要なのはそうした教育の場であり
アートの価値を学ぶ環境ではないでしょうか。
日本におけるアートの役割が明確になれば
外国には負けない文化を価値を創出できるきっかけになるくらい
重要であると考えられます。
近い将来AIによって人間にしか出来ない事が少なくなる中
アートの存在価値はますます上がっていくでしょう。