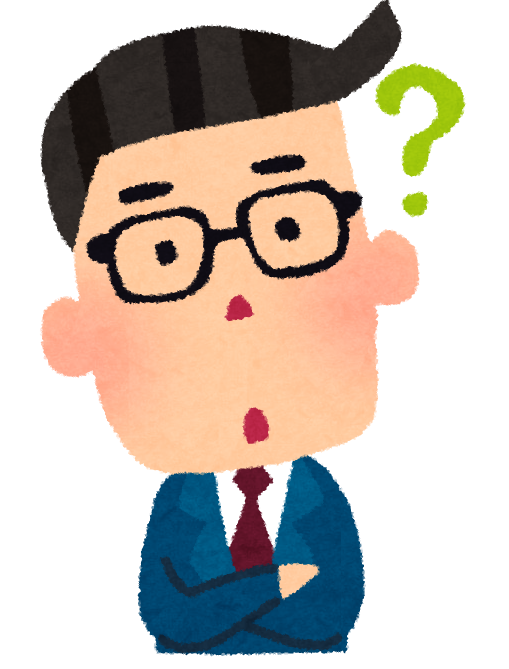先行者優位はどのような分野であったとしても
先に何かを始める事によって優位な立場になれる可能性があり
能力の有り無しに左右されない
誰もが平等に与えられる権利だと言えます。
そんな先行者優位はアートやビジネスで成功する為に
とても重要な要素を持っていて
いつの時代であっても有効な手段として用いられてきました。
本記事では、そんな先行者優位について
アートとビジネスの視点から詳しく解説していきたいと思います。
先行者優位ってなに?【先行者優位のアートとビジネスの関係性】
![先行者優位ってなに?【先行者優位のアートとビジネスの関係性】]()
『先行者優位とは新しい分野にいち早く参入する事で有利な環境を得られること』
簡単に言うと「早いもの勝ち」です。
誰よりも新しい事を早く始める事で
誰にも邪魔される事もなく
価格競争に巻き込まれる事もなく
商品のクオリティを最初から上げる必要もなく
多くの人に認知してもらえる可能性があります。
これはアートであってもビジネスであっても同じで
先に新しい事を始めた人は注目を浴び
その中で評価されれば一気に知名度を上げる事ができます。
ただ、アートとビジネスは似ているようで若干異なる部分もあり
それを理解する事でアートの世界でも
十分に活躍できる環境を手に入れられるようになります。
◆ビジネスでは先にスタートした人が勝つ
『能力がなくても先にスタートした人が勝てるのがビジネスです
先行者優位のメリットは知能が高かったり
知識をたくさん持ってるといった
いわるゆ天才達を出し抜いて成功できる可能性がある事です。
成功者は二分されると言われていて
「めちゃくちゃ優秀」か「めちゃくちゃバカ」か
どちらかになります。
バカというと悪い言葉になってしまいますが
実際はそうではなくて
多くの人は後先いろいろ考え過ぎて
動き出せば利益を得られるのにリスクばかり気して
一歩も足を踏み出す事ができません。
でも、そんなことを気にする事なく
純粋に一歩踏み出せる人は天才をも凌駕する事があります。
世の中「やるかやらないか」で大きく人生が変わります。
このようなことからも
誰よりも早く一歩踏み出せる事が
いかに重要かが分かると思います。
先行者優位に立てる人ほどビジネスでは勝てる確率が上がり
その回数が多ければ多い程
人生の中で継続的に成功し続ける可能性がアップするのです。
◆アートでは先にスタートした人が評価の対象になる
『アートの世界では誰もした事がないことを始めると否定されます』
ピカソを例に挙げて説明すると
ピカソの絵を見て最初誰もがハテナマークを思い浮かべたと思います。
正直言って「下手」な絵と感じた人も少なくないのではないでしょうか。
ピカソにとって、表現というものを突き詰めていった結果が
上手く描くというものではなく、対象を自由な描き方で組み合わせていく事でした。
でも、これはもともとピカソ自体が人気の画家であったことや
画力がある事が浸透していたからこそ
ピカソがそのような絵を描いた事によって
それを見たピカソのファンが賛否両論するようになりました。
つまり、実績が無ければ賛否両論すらならなかった可能性があるという事です。
アートの世界では実績を積んだ人が
世間的に誰もした事のない挑戦をする事で評価の対象になります。
注目を集められない人は注目されない世界なのです。
AI時代にアートで先行者優位に立つ方法
![AI時代にアートで先行者優位に立つ方法]()
『画家として活動を続ける人が有利になる社会になります』
これからAIによって多くの仕事が失われていく中で
画家という職業は人間にしか出来ない仕事として
生き残る事が予想されています。
人それぞれ独自の感性を持っていて、見え方も感じ方も変わり
まったく同じ表現をする事はありません。
AIによって人と人との繋がりが希薄化していく中で
人間は人の温かみやコミュニケーションを求めるようになり
画家は社会的価値をより強めていきます。
今すでにポートフォリオを持っている人や地道に活動を続けている人は
科学の技術によって言葉の壁もなくなり
グローバルに活動できるフィールドを手に入れる事も出来るようになります。
このような背景からも
画家として活動を続けているだけで
先行者優位の活動をしていると言えるのです。
なので今から画家として活動を始めても遅くはありません。
当然、絶対に成功できる保証はないのですが
失敗する確率は確実に減らす事ができると思います。
当たり前ではありますが、画力も必要になります。
でも、今の時代自分を宣伝する方法はたくさんあり
実績が無くてもアピールできるチャンスはいくらでもあるのです。
その環境を利用しない手はありません。
多くの人から注目を集められる先行者優位に立てるタイミングは今だけなので
絵を描く事に興味がある人は
画家という職業を目指してみるといいかもしれません。